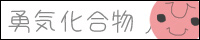『ニューダンガンロンパV3』

お久し振りです。
まだ一部ショップ様では当サークル作品の50%offセールが続いております。
セールの終わらないうちに、是非ご購入を!
……ということで以降は広告消しの駄話です。
しかもまた、『ダンガンロンパ』についてのグチです。
ファンの方はご存じでしょうが今年の1月12日、ファン待望の新作『ニューダンガンロンパV3』が発表され、あちこちで悲嘆の声が巻き起こっています。
アマゾンのレビューが荒れに荒れておりますが、目立つのは「急速に冷めた」という怒りよりは失意の声。絶望ではなく失望。
まあ、グチと書いたようにぼくもそうしたひとりなのですが――そんなわけで、ここに簡単に感想を書き留めておこうと思った次第です。
ネタバレなど気にせずガンガンしますので、ご了承ください。
さて、本筋に入る前に、ちょっと気になったことなど。
今回、発売前に一番危惧されていたのはモノクマの声ではないでしょうか。
個人的に、TARAKOさんの演技は素晴らしいのですが、素晴らしいだけに別な個性を確立してしまい、アイデンティティそのものが大山版とは変わってしまったような感じがします。
また、モノクマーズの父親という設定とTARAKOさんのオトコの子的なボイスはちょっとそぐわない気がしました。声優さんの問題を置くにしても、モノクマというキャラに「父親」という生々しい属性がつくこと自体、ちょっとマイナスだった気がします。
しかし、まあ、それも些末な問題です。
一番の問題は、チャプター5まで賛否はあれど、丁寧に作り込まれた本作が、チャプター6に至って、ちゃぶ台をひっくり返して終わってしまったこと。
また、その設定も逃げを作っておきたかったからか、或いは作り手の間でも混乱があったからか、今一はっきりとしません(ぼく自身は作り手の間で展開についての混乱があったのではと思いますが、それについては後ほど……)。
まず、本作の冒頭でキャラクターたちは「あまりキャラの立っていない地味な制服」で登場し、モノクマーズに「ダメだ、やり直し」と本来の(設定通りの)服装を着せられて、もう一度イントロをやり直させられます。
そのシークエンス、またキャラクターたちのぬいぐるみが糸で吊られているなど、端々で「メタフィクション」を匂わせる描写があったため、何とはなしにオチも予想はできていました。
また、『ダンガンロンパ』初代ではクライマックスでキャラたちが記憶喪失であったことが明かされましたが、『2』では冒頭で「あなたたちは記憶喪失です」と明かし、その上で二転三転がありました。
となれば、本作は冒頭で「仮想世界ネタです」と明かした上での二転三転があるのでは……とプレイ前は想像していました。
が、今回のオチはそれを超えたんだか超えてないんだかよく分からない、微妙なものとなってしまいました。
チャプター6になって正体を現した首謀者(細かい点ですが、従来の作品では「黒幕」と呼ばれていた存在は、本作ではどういうわけか「首謀者」と呼ばれています)は「チームダンガンロンパ」のメンバーだったのです。
そう、首謀者は「制作者自身」でした。
この世界では『ダンガンロンパ』という人気コンテンツが長年、大ブームになっており、今回のコロシアイは実は53作目、つまり「V3」とは「53」という意味だったのです。
首謀者はキャラクターたちに「お前たちはフィクションの中の存在だ」と明かすのですが……そこからがよく分かりません。
実は『ダンガンロンパ』、『スーパーダンガンロンパ2』はただのゲーム、フィクションでした。しかし今回のキャラたちはコロシアイへの参加を自ら志望し、オーディションをくぐり抜けて来た存在であると語られます。その上で、記憶をリセットされ、偽の記憶を植えつけられ、キャラクターとしてコロシアイをしていた……ということらしいのです。
つまり「フィクションはフィクションでも、本人たちの肉体だけはノンフィクション」なんですね。
となると、この『ダンガンロンパ』という人気コンテンツは、表向きには「ただのゲームですよ」とアナウンスして、裏では応募してきた人間の記憶を消し、ガチのコロシアイをさせているのか?
何だかよく分かりません。そこまでしている悪逆非道の組織が大っぴらに存在しているのもヘンだし、百歩譲ってその設定を受け容れるとするなら、視聴者たちはコロシアイをあくまでフィクションと思い込んで楽しんでいるわけで、「コロシアイを楽しむ視聴者たちは悪しき存在」と「チームダンガンロンパ」が批判するのは明らかにヘンです。
また、この真実を明かされてよりは、キャラたちは自分たちをフィクションの存在であるとの前提で行動します。しかし、普通、もし自分が元の記憶を消され、偽の記憶を受けつけられた存在だと知ったら、「本来の自分はどんな人物なのか」をこそ、一番気にするのではないでしょうか。
記憶を改変されただけの彼らを「フィクションのキャラクター」とするのはおかしいし、百歩譲って「記憶=人格」とでも解釈して彼らをフィクションとして割り切ったところで(つまり、肉体が人間のものであっても、人格そのものは完全にフィクションだという解釈をしたところで)、「では元の人物は」という疑問が残ります。
にもかかわらず、彼らはそのことについて、全くの無関心です。
チャプター6ではニコ動的に視聴者たちの悪罵を垂れ流し、「悪しき視聴者と、それに立ち向かうキャラクターたち」という図式で話が進みます。
別にメタフィクションオチが悪いわけではありません。
当初から本作のテーマは「ウソ」であるとアナウンスされており、それもまた、悪いわけではありません。
しかし曖昧で整合性に欠けた設定と稚拙な演出のせいで、本作は結果としてヒット作を世に放った者たちの、それによって自分が縛られてしまったことへの不満と、成功者としての奢りが垂れ流されるばかりの作品となってしまいました。
ですが、これはまだマシな方であり、企画段階では更に、悪意に満ちた設定が考えられていたのではないでしょうか。
それを何とか、多少なりともマイルドにしたのが、完成作だったのではないでしょうか。
例えば、本作には「超高校級のロボット」というのが登場します。
「いくら何でもロボットって何なんだ」と発売前から騒がれていたキャラなのですが、いざプレイすると、そこは割と普通に流されてしまいます。もちろん、彼がロボットであった必然性はドラマの中に充分にあるのですが、それにしても随分あっさりと流すなと。
こういうのって(ぼくの感覚が古いのでしょうが、まあ、一般的には)キャラクターたちに「ロボットってどういうこと?」と充分にリアクションさせ、プレイヤーの心情を代弁させるべきなのですが、恐らくスタッフにしてみれば制作している間に慣れが生じ、そこを簡単に流してしまったのではないでしょうか。
丁寧にリアクションさせるべきを、制作者にしてみれば慣れ親しんだことであるため、つい簡単に流す……というのはありがちな失敗です。
ですが、それは同時に、本作が充分な時間をかけ、練り込まれた作品であることも意味しています。
更に言えば、練り込むうちに、本作は設定が二転三転したのではないでしょうか。
上に書いた冒頭に登場する地味なキャラクターたちのシーンでは、このロボットは「恐らく生身では」と想像される外見で登場します。
企画当初は、この「ロボット」という設定自体が「ウソ」だったのではないでしょうか。
他にも本作には「悪の組織の総統」「宇宙飛行士」「魔法使い」といった「いくら何でもウソだろ」と言いたくなる超高校級が登場します。
宇宙飛行士は「書類を偽造して応募したら、たまたま選考委員の目にとまり、補欠合格した」との設定が語られ、魔法使いは実質的にはマジシャンであるのをそのように自称している。
また「自分の流派は自分と師匠が何となく考えたものだ」などと言っている合気道家もいます。
更にはカルト的「教祖」、「降霊術士」としての一面を持つキャラも登場し、これらもまた「インチキ」と親和性が高い。しかし前者はほとんど正体について語られないまま退場してしまいます。これは恐らく後半で言及されるカルトと、何か結びつく設定が考えられていたのではないでしょうか。
また、当初、「保育士」を名乗っており、実は「暗殺者」……というキャラも登場しましたが、これはむしろ「暗殺者」こそが厨二的妄想、というオチが、いかにもつきそうです。
つまり、(ネットでも発売前、噂されていたのですが)今回の超高校級たちの才能は「ウソ」というのが、当初の設定だったのではないでしょうか。
『ダンガンロンパ』はフィクションである。
だから、彼ら自身も実はごく平凡な高校生たちで、厨二的な自分設定を自ら考え、体感型のロールプレイングゲームを楽しんでいた……当初の本作のオチは、そんなものであったと想像できます。
それが長時間かけて練り込むうち、或いは当初の設定がNGとなり、完成版のような展開に改められたのではないでしょうか。
オーディション風景のキャラたちの言動はその名残であり、まことのキャラもまた、本来は「主人公の正体」といった設定ではなかったか。そうなれば「まこと」という、(つまり苗木誠と敢えて同じ)悪意に満ちたネーミングの理由も、明らかになります。
例のキャラの口癖が「地味に」であるのもまた、「本来の、コスプレする前の、地味キャラである主人公たち」に対する強烈な悪意であると言えそうです。
そう、本来の『ニューダンガンロンパV3』はそんな風に、「凡人を嘲笑」して終わる物語だったのです。
キャラクターたちが「フィクションのキャラにされる前の自分」に対して全く無頓着である理由もまた、「本来予定されていた設定をごっそりオミットして空白が生じたため」であったと考えることで、一応の辻褄があうのです。
もっとも、本来の苗木誠も最初は「何の才能もない平凡な高校生」でした。これは「超高校級」という設定の世界でありながら、主人公はプレイヤーが感情移入しやすい人物でなければならないからでした。
また日向創もそれを推し進めたかのような、「予備科生」の設定が与えられていました。
「全員が才能など持たない高校生」というオチはむしろ、今までの作劇から演繹すれば整合性があるはずです。
「暗殺者」だの「総統」だの「魔法使い」だのは厨二的な肩書きですが、いわゆる厨二キャラは、それそこ田中がそうであったように、「フィクショナルなキャラでも貫ければカッコいい」というテーマにつながることが多い。それと同様に本作のキャラたちも「仮にぼくたちがフィクションの存在でも感じた胸の痛みは本物だ」と主張したのですから、そのように持って行くことは可能だったはずです。
「ぼくたちは超高校級ではない、凡人だ。でも、宇宙飛行士になりたい、探偵になりたいという気持ちは本物だ」との精神論で巨悪を打ち破る展開は、ベタとは言え共感を呼びやすいものでしょう。
そこを敢えてしなかった制作者たちの心理は、本作の「ギフテッド制度」という設定が象徴している気がします。既に「ギフテッド」の側に、つまり成功者になってしまった彼らの奢りは、「プレイヤーと同じ目線で作品世界を楽しむ」ことを許さなかった。
それが、本作がこんな結末を迎えたことの理由だったのではないでしょうか。